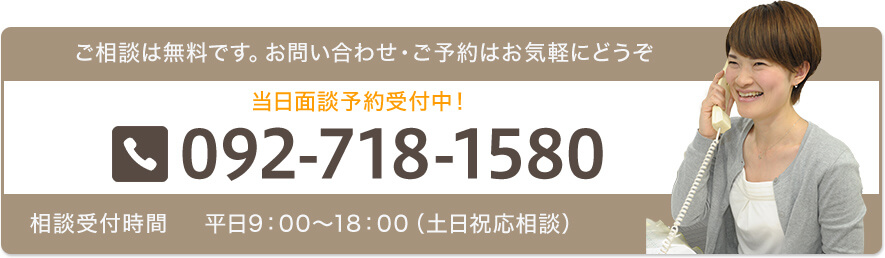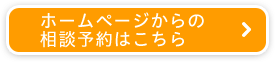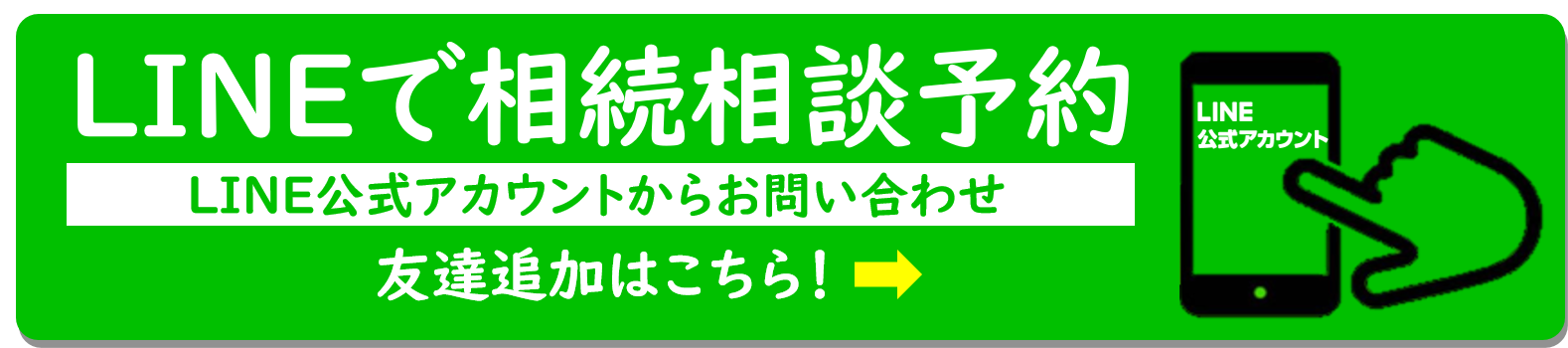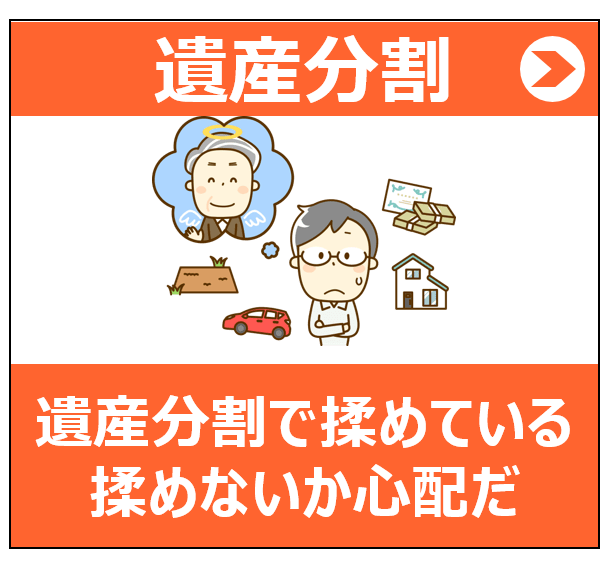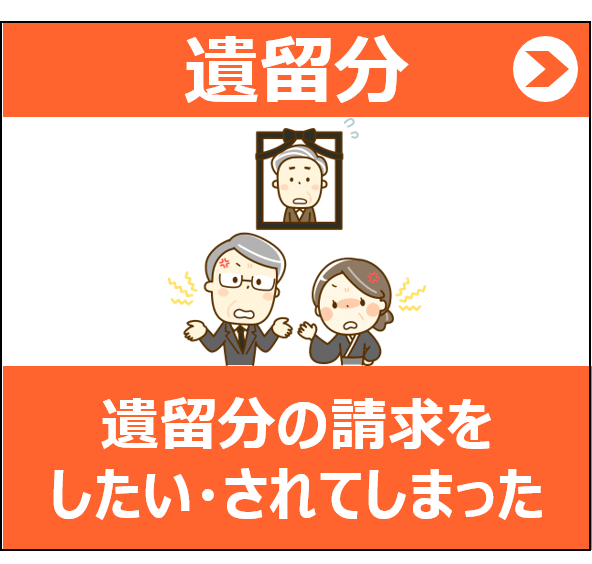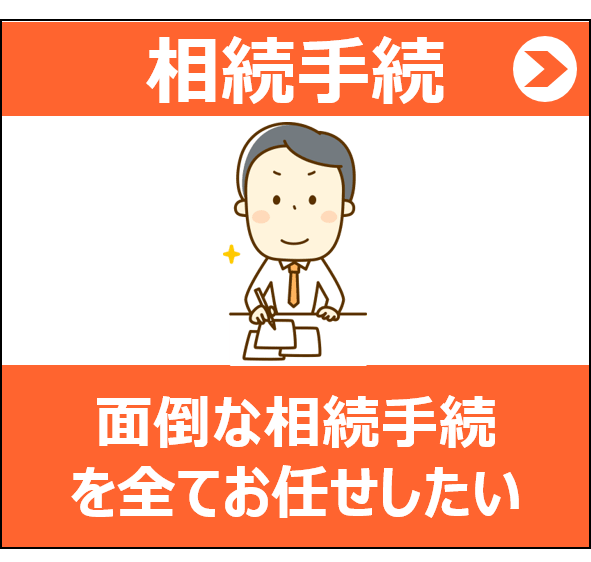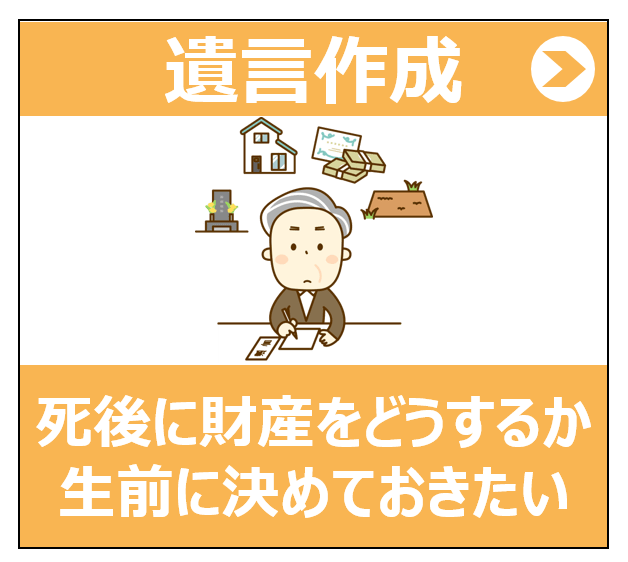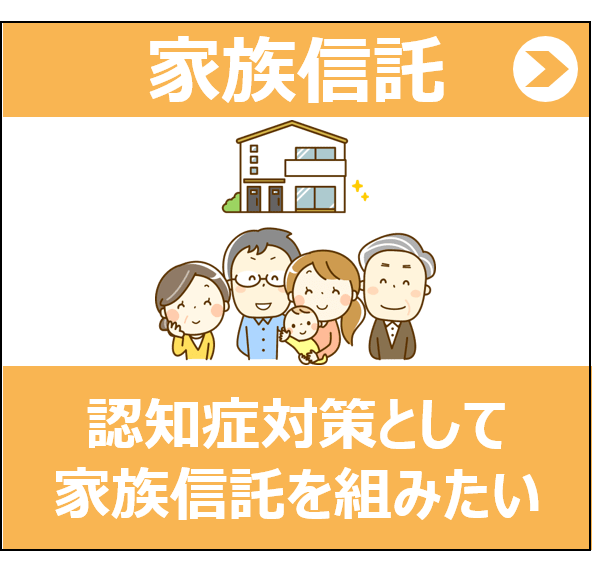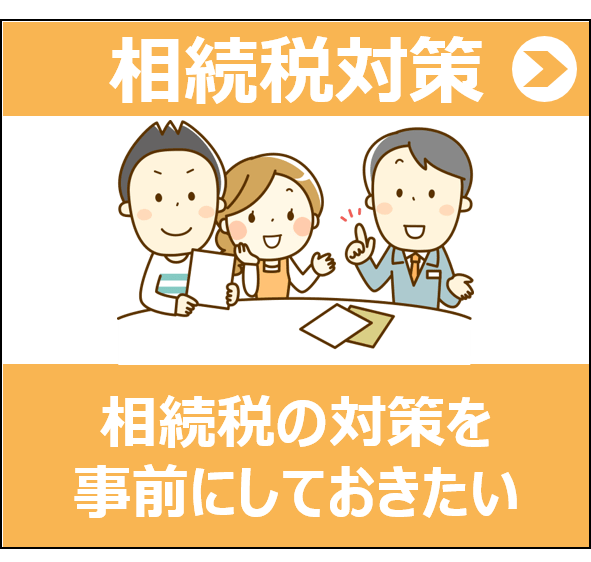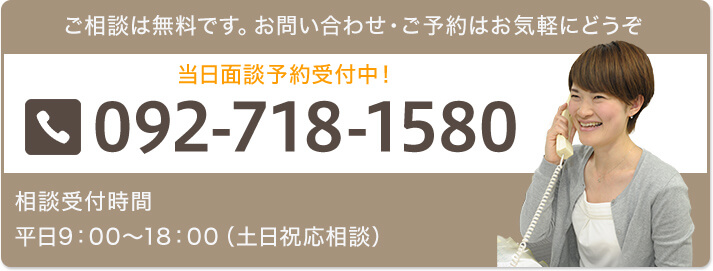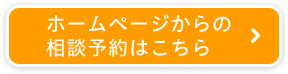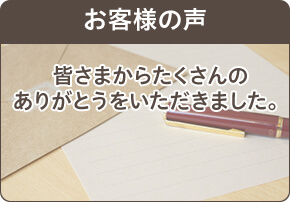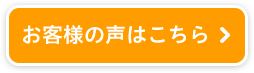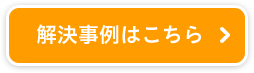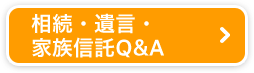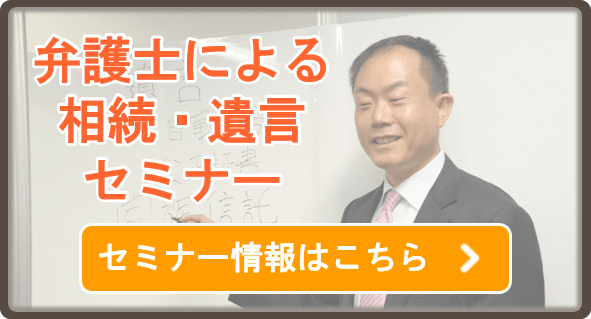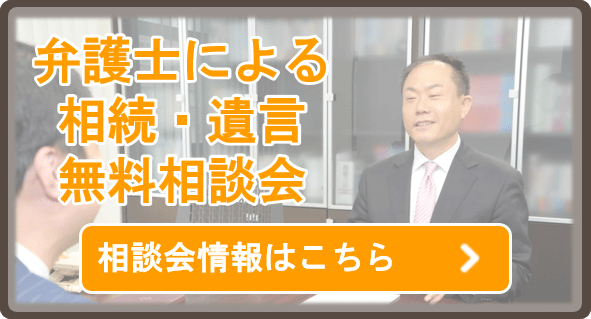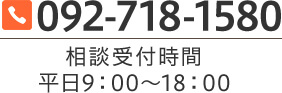賃貸物件を相続する際の注意点とは?相続に強い弁護士が解説!
目次
ご家族が亡くなり、賃貸物件を相続することになったとき、「何から手をつけて良いかわからない」「入居者との関係はどうなるの?」といった不安を感じる方は少なくありません。賃貸物件の相続には、通常の不動産相続とは異なる特有の注意点があります。
この記事では、賃貸物件の相続でよくあるトラブル事例から、手続きの流れ、そして弁護士に相談するメリットまで、相続に強い弁護士が詳しく解説します。
1.賃貸物件での相続でよく発生するトラブル
 賃貸物件(アパート、マンション、一戸建ての貸家など)の相続では、主に以下のようなトラブルが発生しやすいです
賃貸物件(アパート、マンション、一戸建ての貸家など)の相続では、主に以下のようなトラブルが発生しやすいです
(1) 遺産分割時の評価の難しさ
自宅などの不動産と異なり、賃貸物件は収益性(家賃収入)を考慮した評価が必要になり、相続人同士で評価額について意見が対立しやすいです。
また、賃貸物件の場合には、土地や建物に賃借権という権利が付いているため、更地や自用地よりも評価額が低くなることがあり、この評価方法で争いになることがあります。
(2) 家賃収入の帰属をめぐる争い
相続開始から遺産分割協議が成立するまでの期間に発生した家賃収入の帰属を巡って、相続人間でトラブルになることがあります。
相続開始から遺産分割協議が成立するまで(どの相続人が不動産を相続するか決定するまで)の期間に発生した家賃収入は、法的には、各相続人が、その相続分に応じて取得するとされており、その後遺産分割が成立しても、それによって取得できる金額や割合が変更されることはないとされています。
そのため、特定の相続人が単独で家賃を受け取っている場合、その後、他の相続人からその相続人の相続分相当の賃料について、不当利得返還請求をされる可能性があります。そのため、遺産分割協議の成立までに時間がかかり、相続開始から遺産分割までの期間が長くなった場合には、後日の紛争を防ぐためにも、賃料についてもあわせて協議して合意しておくことが望ましいです。
なお、法的な考え方とは別に、相続人全員で合意すれば、最終的に当該不動産を取得する者に遺産分割協議成立までの賃料も取得させるせるということも可能です。
(3) 遺産分割方法の難しさ
賃貸物件は基本的に一つの不動産であるため、相続財産をそのままの形で分ける「現物分割」が難しく、売却して金銭を分ける「換価分割」や、特定の相続人が単独で相続し、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」を検討する必要があります。この分割方法について、相続人間で意見が対立してしまうとトラブルの原因になります。
(4) 共有相続によるその後のトラブル
公平性を重視して賃貸物件を共有名義で相続すると、その後の不動産の売却や建て替え、担保の設定などをするにも共有持分権者全員の同意が必要となり、意思決定が困難になります。
また、世代交代が進むにつれて相続により共有持分が細分化されて権利関係がさらに複雑化し、また共有持分権者間の関係性も希薄になるなど将来的により大きなトラブルに発展する危険性があります。
(5) 賃貸借契約の管理
相続人が複数いる場合、誰が大家としての地位を引き継ぎ、賃貸借契約の管理や修繕義務、更新手続きを行うのか、明確にしておかないとトラブルに発展する可能性があります。
~あわせて読みたい~
2.賃貸物件を相続する際の注意点
(1) 共有名義のリスク
賃貸物件を複数人で共有名義にして相続(共有分割)すると、前記の通り将来的に売却や大規模修繕が必要になった際に、全員の同意が必要となり、スムーズに意思決定することが出来なくなってしまいます。また、世代交代が進むにつれて権利関係がさらに複雑化し、将来的により大きなトラブルに発展する危険性があります。
将来の売却や権利変更を円滑に行うためにも、共有名義を避け、可能な限り単独名義とするよう遺産分割協議を進めるべきです。
(2) ローン残債を巡る問題
賃貸物件にローン残債がある場合、相続人がその債務も引き継ぐことになります。収益性の低い物件で多額のローンが残っている場合、相続人にとって大きな負担となり、場合によっては相続放棄を検討せざるを得ない状況も生じます。
また、ローン残債等の債務は、相続の開始によって、各相続人に相続分に応じて当然に承継されるというのが法的な結論になります。そのため、不動産を取得した相続人が、ローンも全額引き継いで、今後ローンの返済をしていく場合には、事前に金融機関とも相談して、その相続人に債務を集約する手続き(他の相続人に承継された債務を引き受けることになるので、債務引受といいます。)も必要です。
(3) 入居者との賃貸借契約について
賃貸物件を相続した場合には、賃貸借契約の当事者が変わったことを、入居者に書面で通知しておくことが望ましいです。また、入居者に対する敷金の返還義務も相続されます。賃貸借契約終了時に、相続人が賃貸人として入居者に対する敷金の返還義務を負います。さらに、建物の修繕義務も賃貸物件を相続した人に承継されます。
前記のとおり共有分割は避けた方が良いですが、仮に共有で相続した場合は、誰が管理や修繕費の支払いを行うか、管理者を明確に定めておく必要があります。
3.賃貸物件を相続する際の流れ
一般的な賃貸物件の相続手続きは、以下のような流れで進みます。
(1) 遺言書の確認
相続人の確定:まず、故人が遺言書を残していないか確認します。賃貸物件に関する記載があれば、その内容に従います。
(2) 相続財産の調査
評価:賃貸物件の権利関係(借地権、賃借権の有無)や収益性、ローンの残債の有無を確認したうえで、評価を行います。
(3) 遺産分割協議
相続人全員で、誰が賃貸物件を相続するかを話し合います。共有のリスクを避け、単独名義での相続を目指すのが理想的です。
(4) 管理会社や金融機関などに連絡
アパート経営を引き継ぐ相続人が決まったら、不動産管理会社や関係する金融機関に連絡します。金融機関からのローンが残っている場合には、不動産を引き継ぐ相続人による債務引受の手続きも必要ですので、事前に相談しておく必要があります。
(5) 不動産の相続登記(名義変更)
法務局にて、被相続人から新しい所有者(相続人)へ名義を変更する相続登記を行います。令和6年4月以降、相続登記は義務化されているため、相続人は土地や建物などの不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、必ず登記手続きを行う必要があります。
(6) 入居者への通知・管理開始
全ての手続き完了後、新しい大家として、入居者に所有者変更の通知を行い、賃貸物件の管理(家賃の受領、修繕対応など)を開始します。
4.賃貸物件の相続を自分で進めるリスク
 一見単純に見える不動産相続ですが、賃貸物件の場合は特に専門的な判断が求められます。
一見単純に見える不動産相続ですが、賃貸物件の場合は特に専門的な判断が求められます。
自身で進めると、次のようなリスクが生じます。
(1) 法的手続きの複雑さ・大変さ
相続登記や税務申告など、専門的知識を要する手続きが多く、誤った手続きにより後々大きな問題に発展する可能性があります。
また、必要書類の収集、各種手続きの実施、関係機関との調整など、相続手続きには膨大な時間と労力が必要です。仕事や日常生活との両立が困難になることも少なくありません。
(2) 適正な評価ができないリスク
賃貸物件の評価は複雑で、適切な評価方法を知らないと、他の相続人との間で不公平な分割になってしまう可能性があります。
(3) 遺産分割協議の長期化
感情的な対立が生じやすい相続問題において、特に賃貸物件のような高額資産では、わずかな認識の違いが大きな争いに発展します。相続人間だけで話し合いを進めていくと、対立によって話し合いが進まず、遺産分割協議が長期化してしまうおそれがあります。
5.賃貸物件の相続を弁護士に依頼するメリット
(1) トラブルの未然防止・解決
相続人間の意見対立を調整し、法的な根拠に基づいた適正な評価と遺産分割案を提示することで、トラブルの発生を防ぎ、既に発生しているトラブルも解決へ導くことができます。
(2) 適正な評価と分割の実現
賃貸物件の特殊性を踏まえ、適正な評価額を算出し、共有状態を避ける最善の分割方法(代償分割など)を提案・実現します。
(3) 煩雑な手続きの一括代行
相続人の確定、財産調査、遺産分割協議書の作成など、煩雑な手続きを代行し、煩雑な手続きから解放され、お客様が心身ともにゆとりをもって次のステップに進めるようサポートします。
(4) 専門家との連携
必要に応じて税理士、司法書士、土地家屋調査士など各分野の専門家と連携して最適な解決策を提供します。
(5) 将来を見据えたサポート
相続する賃貸物件の賃貸管理や不動産の売却・活用についても、将来的な視点を含めた専門的なアドバイスが受けられます。また、相続完了後も、賃貸経営に関する法的アドバイスや、将来の相続対策まで継続的にサポートを受けることができます。
6.賃貸物件の相続は弁護士法人岡本綜合法律事務所へご相談ください
賃貸物件の相続は、登記・契約・税務など複数の専門知識が必要になる複雑な手続きです。ご自身で対応するよりも、早期に専門家へ相談することで、トラブルを防ぎ、円滑に相続を進めることができます。
また、弊所では、弁護士歴25年以上の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士が在籍しておりますので、豊富な経験に裏打ちされたアドバイスを行うことができます。弊所では、相続や遺産分割が泥沼の紛争に発展する前に、早い段階でご相談にお越しいただきたいという思いから、お気軽にご相談いただけるように、相続相談の初回相談料を60分無料としております。
お早めに弁護士にご相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決に繋がります。
無料相談のお申し込みは、お電話・メール・LINEで受け付けております。お気軽にお申込みください。
以上
弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
LINEでも相談予約いただけます!
当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
5、初回相談は無料
遺産相続のメニュー