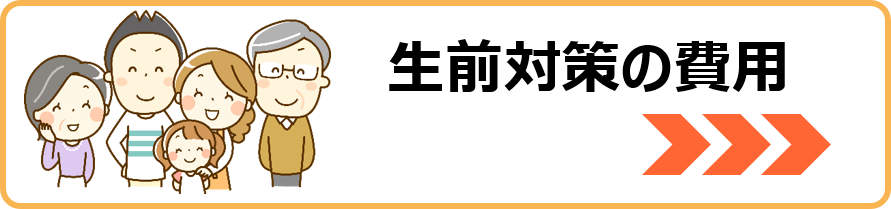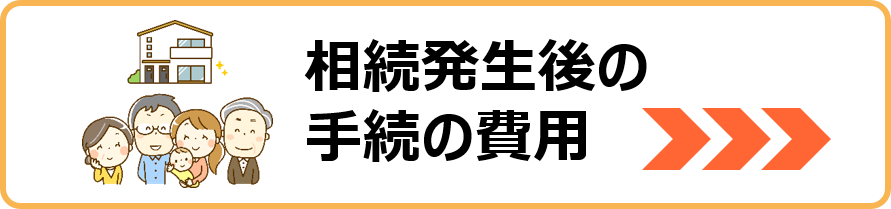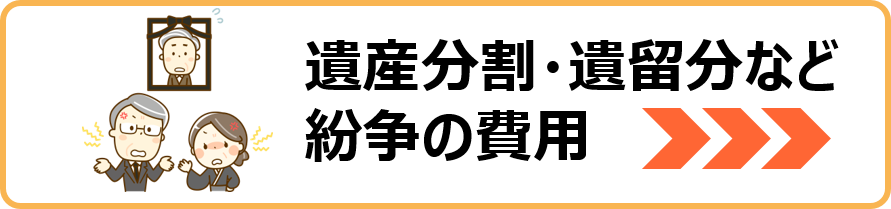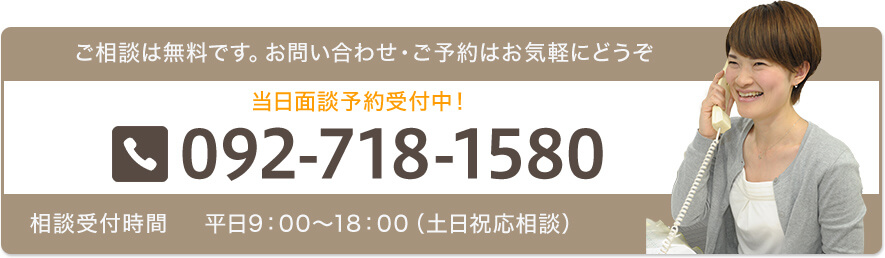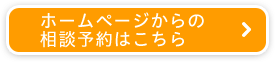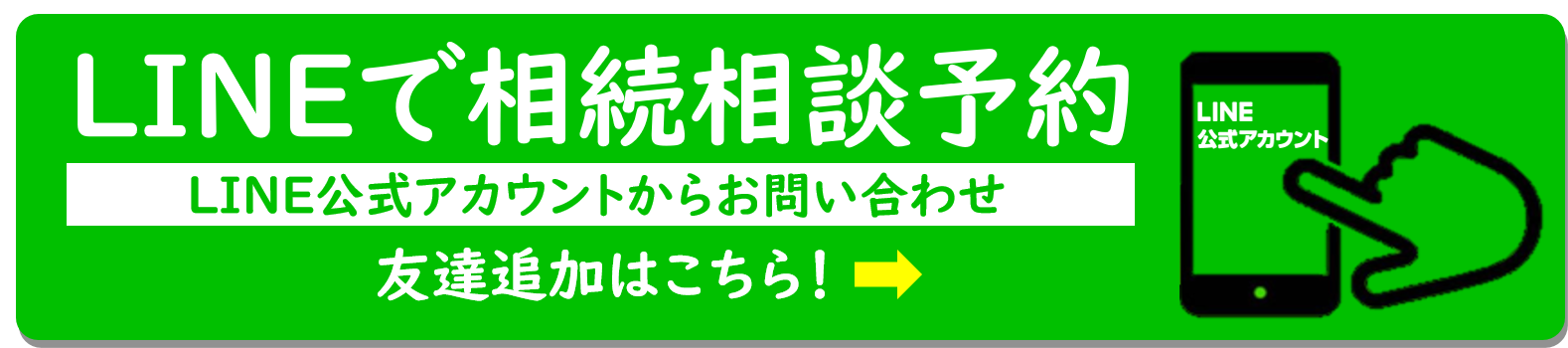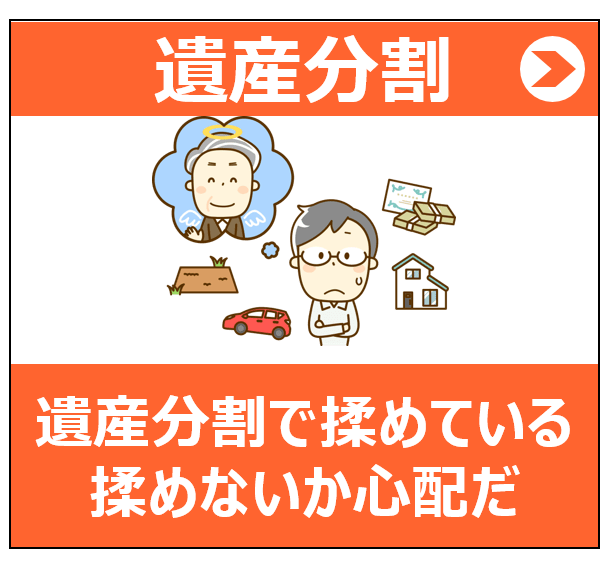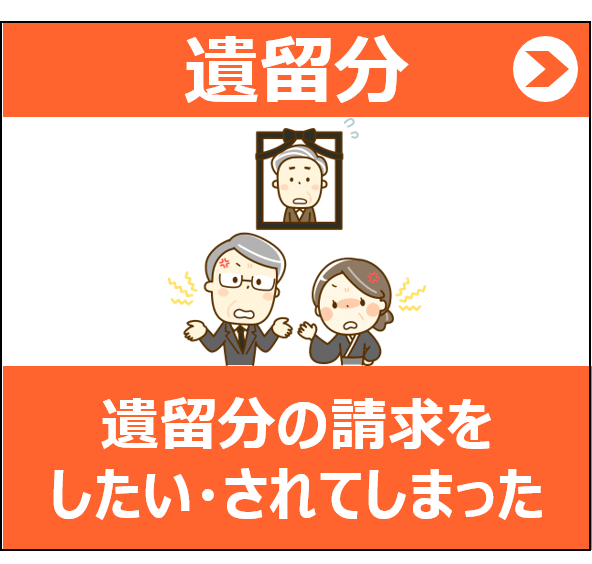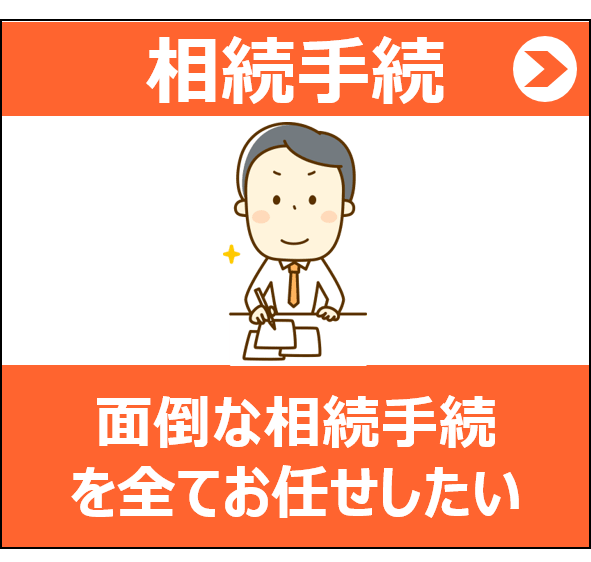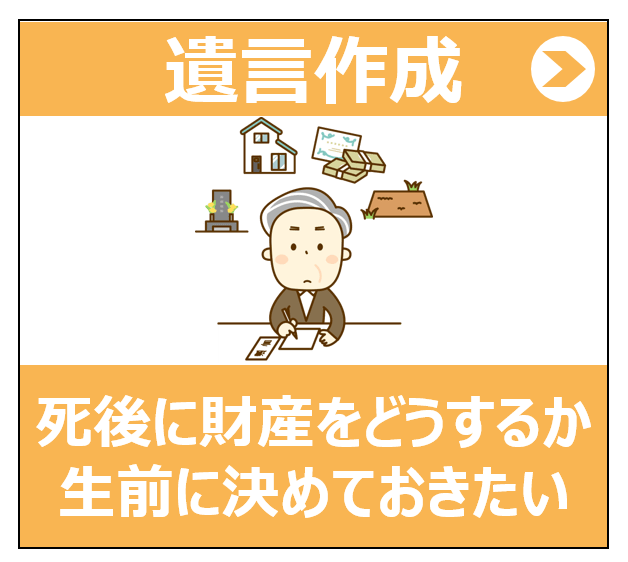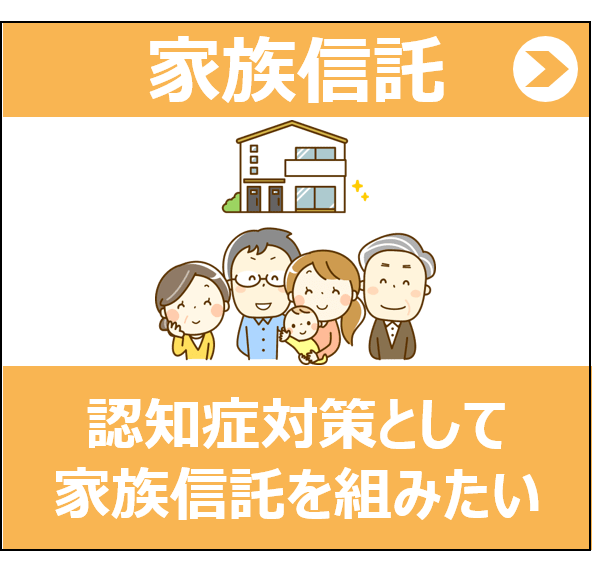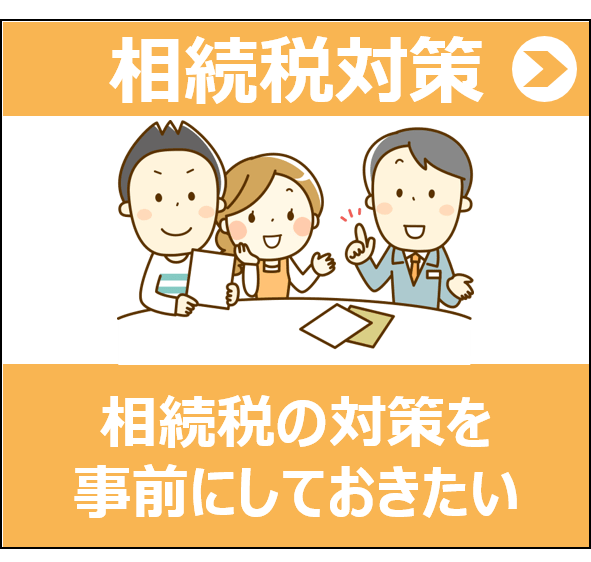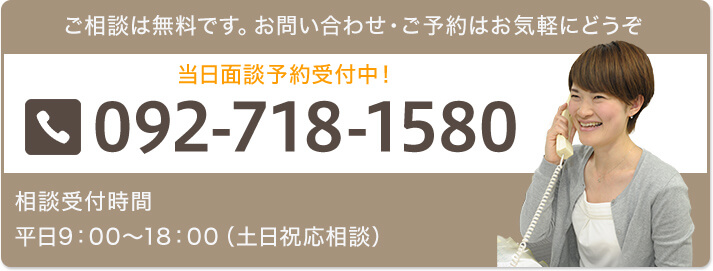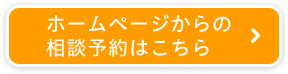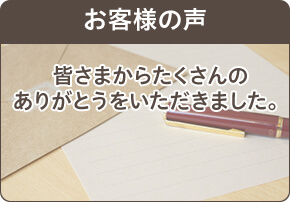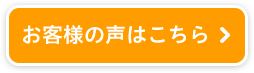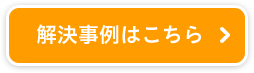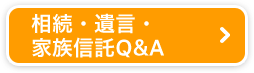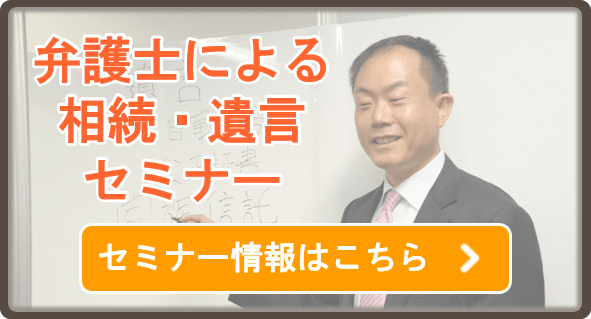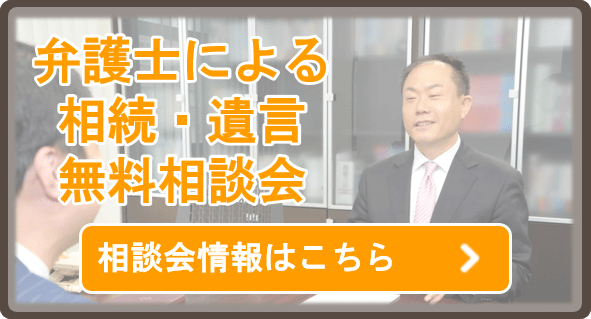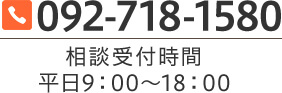弁護士費用
弁護士費用の種類
弁護士費用に関する説明
※ 別ページに移動します。
弁護士への相談費用
初回相談料:無料(60分)
2回目以降:5,500円(税込)/30分
※セカンドオピニオンのご相談は有料対応とさせていただきます。詳細についてはこちらからご覧ください。
※当事務所の無料会員制度にご加入いただきましたら、年間2回までのご相談が無料となります。詳しくはスタッフにお声かけください。
生前対策の費用
遺言書作成
お客様が希望される遺言の内容を、法的に問題ないように条項に反映する手続き(※遺言作成を代行するだけの手続き)です。
遺言内容のアドバイスや提案をご希望の場合には、下記『遺言コンサルティングサポート』をご覧ください。
| 相続財産の価額 |
弁護士費用(税込) |
| 5000万円以下の場合 | 11万円~ |
| 5000万円を超え1億円以下の場合 | 16.5万円~ |
| 1億円を超える場合 | 22万円~ |
※ 公正証書遺言を作成する場合には、上記料金に3.3万円(税込)を加算させていただきます。
※ 公正証書遺言を作成する場合には、別途、公証人に支払う手数料及び証人の日当(※当事務所にて証人を手配する場合のみ)がかかります。
遺言コンサルティングサポート
『遺言コンサルティングサポート』とは、お客様の現状や、遺言内容のご希望を確認したうえで、内容のアドバイス・提案・実際の作成手続きも実施するサポートです。
遺留分対策等についてもアドバイスさせていただくため、争族対策に適しています。
単に、遺言書の作成を代行する業務ではなく、お客様が後悔しないような、最適な遺言を作成するためのサポートを実施しています。
「遺言内容についてのアドバイスが欲しい。」「自分の家族や親族の状況に『最適な遺言書』を作ってほしい。」といった方に、お勧めのサポートです。
| 相続財産の価額 |
費用(税込) |
|---|---|
| 4000万円未満の場合 | 22万円~ |
| 4000万円以上8000万円未満の場合 | 33万円~ |
| 8000万円以上1億円未満の場合 | 44万円~ |
| 1億円以上の場合 | 要見積り |
遺言作成と動画撮影のセット
弁護士による遺言書案の作成・アドバイスに加えて、作成時の様子を動画で撮影するサービスです。
費用:上記記載の遺言作成費用+11万円(税込)
遺言診断
既に作成されている遺言について、作成当時からの状況の変化等も踏まえて、現在の状況にも適した内容になっているかを診断させていただくサービスです。
費用:無料
遺言診断後の書き直し
無料診断を受けていただいた後、遺言の書き直しをご希望の場合に、ご案内させていただくサービスです。
費用:遺言コンサルティングサポート記載の費用から、5.5万円(税込)値引き
遺言執行
| 相続財産の価額 | 弁護士費用(税込) |
| 300万円以下の場合 | 33万円~ |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 相続財産の価額の2.2%+26.4万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 相続財産の価額の1.1%+59.4万円 |
| 3億円を超える場合 | 相続財産の価額の0.55%+224.4万円 |
※ 遺言執行にかかる経費実費は別途必要になりますので、ご了承ください。
※「相続財産の価額」は、積極財産の価額の合計額を指し、債務控除前・相続税における各種特例の適用前の金額とします。
不動産については、固定資産税評価額に1.3を乗じた金額を基準とします。
ご不明点がございましたらお問い合わせください。
家族信託(民事信託)組成サポート
信託を組成するか否か、また、信託を組成する場合にどのようなスキーム(=どのような計画で進めるか)が望ましいのかというご相談をお受けします。
また、信託を組成する場合の契約書の作成や、関係者の手配・交渉などのサービスをご提供しています。
認知症対策、争族対策、相続税対策に適したサポートです。
|
信託財産の 評価額 |
手数料(税込) |
内容 |
|
1億円以下の場合 |
1.1% ※3,000万円以下の場合は、 |
・謄本、評価証明等の収集 ・相続人調査確定作業 (戸籍調査収集・相続関係説明図作成) ・家族信託設計コンサルティング ・公証役場への立会い ・信託登記 ・家族信託導入後のメンテナンス |
|
1億円を超え3億円以下の場合 |
0.55%+55万円 |
|
|
3億円を超え5億円以下の場合 |
0.33%+121万円 |
|
|
5億円を超え10億円以下の場合 |
0.22%+176万円 |
|
|
10億円を超える場合 |
0.11%+286万円 |
その他以下の費用が発生します。
①信託契約書を公正証書にする場合
➡公証役場にかかる実費
②信託契約書の作成費用
➡16.5万円(税込)
③信託財産に不動産がある場合
➡登録免許税、司法書士費用
④信託管理人弁護士費用
➡月額1.1万円(税込)
※その他郵送費等の実費が発生します。
財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約
財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約に関する、契約書の作成費用です。
| 財産管理委任契約 | 11万円(税込)~ |
| 任意後見契約 | 22万円(税込)~ |
| 死後事務委任契約 | 11万円(税込)~ |
※契約書を公正証書で作成する場合は、別途、公証人へ支払う手数料がかかります。
相続発生後の手続の費用
相続人調査・相続財産調査お任せプラン
遺産分割を始めるときに必要な「相続人の数」「相続財産の額・種類」「遺言の有無」等を調査し、今後の遺産分割の方針をご提案させていただくサービスです。
サービス内容
費用 : 22万円(税込)
①相続人調査及び確認
②相続関係説明図作成
③相続財産調査(不動産、預貯金など)
④遺産分割方法に関するご提案
※名寄帳は2つまで。金融機関は5つまで。それ以上の場合は1社につき1.65万円となります。
※金融機関が県外になる場合は別途お見積りとなります。
円満遺産分割サポート
相続で連絡を取りたくない・連絡が取れない相続人がいる場合、弁護士が間に入り、トラブルに発展しないよう、円満な相続・遺産分割のお手伝いをします。ただし、調停等の手続に進まざるを得ない場合には、「遺産分割調停・審判」記載の弁護士費用が必要になりますのでご了承ください。
【着手金】
22万円(相続調査手数料の内金11万円を着手金の一部に充当)
【報酬金】
| 相続財産の価額 | 報酬金(税込) |
| 1000万円以下の場合 | 33万円 |
| 1000万円を超え5000万円以下の場合 | 相続財産の価額の3.3% |
| 5000万円を超え1億円以下の場合 | 相続財産の価額の2.2% |
| 1億円を超える場合 | 別途お見積り |
※相続手続きの代行をご希望の方は、下記の「相続手続き丸ごとサポート」をご提案いたします。
(当該プランによって手続きを行う相続人については、10名を上限といたします。ご希望の場合には、追加で「相続手続き丸ごとサポート」の手数料を頂戴いたしますので、ご了承ください。)
相続手続き丸ごとサポート
遺産分割協議書の作成・相続に関する手続・相続財産の分配までを、一括してサポートするプランです。(※相続人間で争いがないことが前提になるサービスです。)
相続に関する手続きは、年金手続、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など、多岐にわたります。
これらの手続きは、申請対象がそれぞれ異なるため、相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはならず、非常に煩雑です。
相続手続き丸ごとサポートでは、弁護士が相続人の皆様の窓口となり、煩雑な相続手続きを全て一括でお引き受けします。なお、経費実費は別途必要になりますので、ご了承ください。
サービス内容
① 戸籍謄本の取得
② 相続財産目録の作成
③ 遺産分割協議書の作成
④ 保険金の請求
⑤ 有価証券の名義変更
⑥ 不動産の名義変更
⑦ 預貯金の名義変更(大手銀行、地銀、信金、ゆうちょ銀行など)
⑧ 換価回収した金銭の相続人への分配手続
⑨ 相続税の申告について税理士を紹介
➉ 年金手続について社労士を紹介
| 相続財産の価額 | 弁護士費用(税込) |
| 300万円以下の場合 | 16.5万円 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 相続財産の価額の 2.2%+9.9万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 相続財産の価額の 1.1%+42.9万円 |
| 3億円を超える場合 | 要見積り |
※経費実費(名義変更に要する費用・税理士費用・社労士費用 等)は別途必要になりますので、ご了承ください。
※「相続財産の価額」は、積極財産の合計額を指し、債務控除前・相続税における各種特例の適用前の金額とします。土地については路線価に基づいた評価額、建物については固定資産税評価額を基準とします。
ご不明点がございましたらお問い合わせください。
相続調査
公正証書遺言の有無の調査
➡1.1万円
相続人調査と相続人関係図作成
➡5.5万円
※相続人は5名まで。6名以上の場合は追加料金が発生いたします。
相続財産調査
➡16.5万円
※名寄帳は2つまで。金融機関は5つまで。それ以上の場合は1社につき1.65万円となります。
※金融機関が県外になる場合は、別途お見積りとなります。
預金の使い込み調査(簡易プラン)
➡11万円
使途が明らかでない出金を判明させるため、簡易的な手続で調査を行います。その結果から、今後の対応などについてお伝えします。
※金融機関は5つまで。それ以上は1社につき1.65万円となります。
※金融機関が県外になる場合は、別途お見積りとなります。
預金の使い込み調査(徹底プラン)
➡33万円
医療機関へ照会を行い、介護記録などを確認して、判断能力の有無を調査します。そのうえで、使い込みがあったかどうか、また、想定される使い込みの金額などを提示いたします。
さらに、訴訟提起した場合に、勝訴できるかの見込みもお伝えします。
※金融機関は10つまで。それ以上は1社につき1.65万円となります。
※金融機関が県外になる場合は、別途お見積りとなります。
遺言の有効性の調査
➡33万円
介護記録などを確認して、判断能力の有無を調査します。必要な場合には、筆跡鑑定が可能な外部の調査機関を紹介します。これらの調査結果をもとに、遺言の有効性を、総合的に検討します。
また、遺言無効確認訴訟についての可否もお伝えします。
遺産分割協議書作成
相続人の間で、すでに遺産分割協議が整っていて、遺産分割協議書の作成のみをご依頼いただく場合の料金です。遺産分割協議書作成のために、資料の取り寄せが必要となる際は、別途経費実費が必要となりますので、ご了承ください。
※他の相続人との協議が整っておらず、交渉が必要な場合は、遺産分割交渉事件の基準による弁護士費用が必要です。
定型の遺産分割協議書作成
| 相続財産の価額 |
弁護士費用 (税込) |
| 5000万円以下の場合 | 11万円~ |
| 5000万円を超え1億円以下の場合 | 16.5万円~ |
| 1億円を超える場合 | 22万円~ |
非定型の遺産分割協議書作成
|
相続財産の価額 |
弁護士費用(税込) |
| 300万円以下の場合 | 22万円 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 相続財産の価額の 1.1%+18.7万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 相続財産の価額の 0.33%+41.8万円 |
| 3億円を超える場合 | 相続財産の価額に 0.11%を乗じた金額+107.8万円 |
※「相続財産の価額」は、積極財産の合計額を指し、債務控除前・相続税における各種特例の適用前の金額とします。土地については路線価に基づいた評価額、建物については固定資産税評価額を基準とします。
ご不明点がございましたらお問い合わせください。
遺産分割・遺留分など紛争費用
遺産分割紛争
遺産分割交渉
【着手金】
| 請求する遺産額 | 弁護士費用(税込) |
| 420万円以下の場合 |
33万円 |
| 420万円を超え3000万円以下の場合 | 請求する遺産額の 5.5%+9.9万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 請求する遺産額の 3.3%+75.9万円 |
| 3億円を超える場合 | 請求する遺産額の 2.2%+811.8万円 |
【報酬金】
| 獲得した遺産額 | 弁護士費用(税込) |
| 420万円以下の場合 | 66万円 |
| 420万円を超え3000万円以下の場合 | 獲得した遺産額の 11%+19.8万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 獲得した遺産額の 6.6%+151.8万円 |
| 3億円を超える場合 | 獲得した遺産額の 4.4%+811.8万円 |
遺産分割調停・審判
【着手金】
| 請求する遺産額 | 弁護士費用(税込) |
| 820万円以下の場合 |
55万円 |
| 820万円を超え3000万円以下の場合 | 請求する遺産額の 5.5%+9.9万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 請求する遺産額の 3.3%+75.9万円 |
| 3億円を超える場合 | 請求する遺産額の 2.2%+811.8万円 |
【報酬金】
| 獲得した遺産額 | 弁護士費用(税込) |
| 520万円以下の場合 | 77万円 |
| 520万円を超え3000万円以下の場合 | 獲得した遺産額の 11%+19.8万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 獲得した遺産額の 6.6%+151.8万円 |
| 3億円を超える場合 | 獲得した遺産額の 4.4%+811.8万円 |
※ 調停・訴訟通じて3期日(WEB・電話での出廷も含む)まで上記着手金に含みます。第4回調停期日からは、出廷日当(WEB・電話での出廷も含む)として、44,000円/回をいただきますのでご了承ください。
遺産分割紛争の着手金・報酬金について
※ 別ページに移動します。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求をしたい場合
【着手金】
| 請求する遺留分額 | 弁護士費用(税込) |
| 420万円未満の場合 |
33万円 |
| 420万円以上3000万円未満の場合 | 請求する遺産額の5.5%+9.9万円 |
| 3000万円以上3億円未満の場合 | 請求する遺産額の3.3%+75.9万円 |
| 3億円以上の場合 | 請求する遺産額の2.2%+811.8万円 |
【報酬金】
| 獲得した遺留分額 | 弁護士費用(税込) |
| 420万円未満の場合 | 66万円 |
| 420万円以上3000万円未満の場合 | 獲得した遺産額の11%+19.8万円 |
| 3000万円以上3億円未満の場合 | 獲得した遺産額の6.6%+151.8万円 |
| 3億円以上の場合 | 獲得した遺産額の4.4%+811.8万円 |
※ 調停・訴訟通じて3期日(WEB・電話での出廷も含む)まで上記着手金に含みます。第4回調停期日からは、出廷日当(WEB・電話での出廷も含む)として、44,000円/回をいただきますのでご了承ください。
遺留分侵害額請求をされた場合
【着手金】
| 請求される遺留分額 | 弁護士費用(税込) |
| 820万円未満の場合 |
55万円 |
| 820万円以上3000万円未満の場合 | 請求される額の5.5%+9.9万円 |
| 3000万円以上3億円未満の場合 | 請求される額の3.3%+75.9万円 |
| 3億円以上の場合 | 請求される額の2.2%+811.8万円 |
【報酬金】
| 請求を免れた額 | 弁護士費用(税込) |
| 520万円未満の場合 | 77万円 |
| 520万円以上3000万円未満の場合 | 請求を免れた額の11%+19.8万円 |
| 3000万円以上3億円未満の場合 | 請求を免れた額の6.6%+151.8万円 |
| 3億円以上の場合 | 請求を免れた額の4.4%+811.8万円 |
※ 調停・訴訟通じて3期日(WEB・電話での出廷も含む)まで上記着手金に含みます。第4回調停期日からは、出廷日当(WEB・電話での出廷も含む)として、44,000円/回をいただきますのでご了承ください。
よくあるご質問
可能です。
実際に争いが起こる前にご相談頂き,争いを未然に防ぐ方法がないか検討したり,起こり得る争いに備えて事前に対策を考えたりすることもできますので,少しでもご不安なことがございましたら,遠慮なくご相談下さい。
次のような資料をご準備頂けると相談をより具体的かつスムーズに進めることができます。
・ 相続関係が分かる資料(相続関係図やお手元にある戸籍謄本等)
・ 被相続人の財産が分かる資料(資料としては通帳や保険証券,不動産の全部事項証明書等が考えられますが,お手元にない場合には財産を書き出したメモでも構いません。)
・ その他,遺言書や,敵対関係にある方から送られてきた手紙等,ご相談に関係する資料をお持ちください。
遺言作成の場合は,打合せの上で,必要な戸籍の取り寄せ,遺言書案の作成,(公正証書遺言の場合は)公証役場との打合せや日程調整,公正証書作成時の公証役場への同行等一連の手続きをほぼお任せいただけます。
相続人・相続財産調査の場合にも,打合せの上で,必要な戸籍の取り寄せ,法務局への法定相続情報の申請,各金融機関等への照会,相続財産調査報告書の作成等の一連の手続きをほぼお任せいだたけます。
交渉事件では,相手方への通知文書の作成・送付,交渉,遺産分割協議書等の作成を行います。調停,訴訟等の法的手続きをご依頼いただいた場合には,裁判所への出頭(ただし,調停の場合はご依頼者様にもご同行頂く必要がある場合も多いです。),書面の作成・提出等を行います。
共有不動産とは、1つの不動産を複数人で共有している状態の不動産のことです。共有不動産の売却には共有者全員の合意が必要になります。そのため、共有不動産の売却を希望する場合でも、共有者のうちの1人が同意しないときには、共有不動産を売却することができません。
このような事態への対処としては、共有状態を解消することが考えられます。共有状態の解消には以下の方法が考えらえます。
ご自身の持分を売却する方法
ご自身の共有持分については、他の共有者の同意を得ることなく、自由に売却できます。
ご自身の持分を第三者に売却する際には、共有持分を専門に扱う不動産業者の利用が考えられます。もっとも、持分の売却については、売却や利用の制約があることから、売却価格は相当程度低くなる傾向にあります。
また、ご自身の共有持分を第三者に売却するのではなく、他の共有者に売却することも考えられます。共有不動産の売却に同意しない共有者については、その不動産を手放したくないという考えの場合もあり、そのような場合には持分の買い取りに応じる可能性もあると考えられます。
相手の持分を買い取る方法
資金に余力があり、またご自身の共有持分の割合が大きい場合には、他の共有者の共有持分を買い取り、単独で所有権を持ち、そのうえで不動産を売却するという手段が考えられます。
この場合、他の共有者との間で持分についての売買契約を成立させる必要があります。共有不動産の売却に同意しない共有者との間で、持分の売買契約を成立させることは難しいものになることが考えられます。
共有物分割による方法
共有者間の協議によって共有物分割を行うことも考えられます。共有者間でどのような共有物分割を行うかにつき合意できる場合には、その分割方法は基本的に自由に決めることができます。
共有物分割について共有者間の協議が調わない場合には、裁判所において共有物分割調停や共有物分割請求訴訟により解決することになります。
裁判による共有物分割には、現物分割、代償分割、換価分割があります。
(1)現物分割
現物分割とは、共有物を物理的に分割することをいいます。建物の場合は、建物自体を物理的に分割することは現実的に困難ですので、現物分割が採用されることは基本的にないと考えられます。土地の場合は、共有持分の割合に応じて分筆することが考えられますが、土地の形状、面積などから分筆が現実的ではない事例が多く、あまり行われていません。
(2) 代償分割
代償分割とは、共有者の一部が共有物を取得し、その他の共有者に対して代償金を支払う分割方法です。代償金の金額については、共有物件を時価評価したうえで、共有持分の割合に応じて、共有物件を取得しない共有者が受け取るべき金額を算定します。
代償分割は、不動産を処分したい者にとっては代償金を受領でき、また不動産を手放したくない者にとっては不動産の保有を続けられるという点では双方にとって受け入れやすい解決方法といえます。しかしながら、評価額の高い不動産などでは、代償金を支払うだけの資金力がないなどの理由で行えないこともあります。
(3) 換価分割
換価分割とは、共有物を売却し、売却代金を共有者間で分ける分割方法のことをいいます。換価分割の場合、一円単位で売却代金を分けられるため、共有持分割合に応じた公平な分割が実現できるメリットがあります。その反面、共有物自体がどの共有者の手元にも残らないことになります。
判決による場合、競売を命じる判決を得て、競売による売得金から諸経費を控除した残金を共有持分の割合に応じて取得することになります。最近は、競売でも、時価に近い価格で競落される例が多いものの、競売の場合にはいくらで売却されるか分からないという不安定さがあることと、手続に8ヶ月程度かかるという問題があります。そのため、当事者間で話ができる場合には、任意売却によって共有状態を解消することもよく行われています。
まとめ
ご自身の共有持分を他の共有者などに売却することや、逆に他の共有者の持分を買い取るなどの方法について話し合いで解決することも考えられます。話し合いで解決できるのであれば、比較的に短い期間での解決が可能になります。
しかし、話し合いで解決できない場合でも、最終的には共有物分割請求訴訟を提起して、判決を得て共有状態を解消することは可能ですので、最終的には何らかの解決が可能ということになります。ただし、手続には専門的な知識が必要ですので、是非、不動産に詳しい弁護士に御相談ください。
なお、共有者の一部の所在が不明な場合の対応について、2023年(令和5年)4月1日から新たな制度が創設されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
基本的に平日の午前9時~午後6時までの営業時間内で相談をお受けしています。
ただし,営業時間内にお越し頂くことが難しい場合には,事前に日程調整させて頂いた上で,土日や営業時間外でもお受けできる場合がありますので,まずはお問い合わせください。
まずはお電話や当サイトお問い合わせフォームやLINE公式アカウントからご連絡頂きましたら,ご相談の日程調整をさせて頂きます。
ご相談日には,ご相談内容に応じた対応策や弁護士費用の概算額をご提案致します。必要に応じて,見積書を発行することも可能です(ご相談内容が複雑な場合には,見積書はご相談後に改めてお送りすることもございますので,ご了承ください。)。
その後,実際にご依頼頂くこととなりましたら,改めて委任契約の締結,委任状の作成,弁護士費用のご入金を頂いた上で事件に着手させて頂くこととなります。
交渉ではお話しがまとまらずに調停へ移行する際や,調停だけでは解決できずに,別途訴訟提起が必要な場合などに追加の着手金が発生する場合もございますが,その場合には委任契約の段階で事前にご説明させて頂き,ご依頼者様のご承諾を頂いた上で委任契約を締結致しますので,ご安心ください。また,事件終了時には,着手金と別途,獲得できた経済的利益に応じて報酬金も発生しますが,これについても委任契約書に金額の算定方法を明記しております。
なお,遺言書作成や相続人・相続財産調査等については御依頼時に手数料をお支払いいただいた後は,事件終了時まで追加の弁護士費用が発生することはありません(※ただし,相続人・相続財産調査後に遺留分侵害額請求等を行う場合には,別途委任契約を締結して頂き,事件に応じた着手金及び報酬金が発生しますので,ご留意ください。また,いずれの案件も経費実費は別途頂くこととなります。)。
可能です。
お話しを伺った上で,想定される対策を検討し,対策に応じたお見積りを致します。
相談は可能です。
ただし,事実関係を詳細に把握されているご本人様による相談の方が,より適切なアドバイスが可能と思われます。また,実際にご依頼いただく際には,必ずご本人様の意思確認をさせて頂きます。また,ご相談の際には,『より効果的に相談を進めるため,無料相談の際に準備した方が良いものは?』でお答えした資料をお持ちください。
可能です。
当事務所では,予め日程調整をしたうえで,ZOOM,Microsoft Teams等によるビデオ相談も行っておりますので,お気軽にお問い合わせください。なお,お電話でのご相談はお受けしておりませんので,予めご了承ください。
ご依頼いただく内容,相続人の人数,相続財産の種類や量,すぐに相続人間で合意ができるか否か等によって解決までの時間は異なります。
相続人・相続財産調査で2ヶ月~3ヶ月程度,交渉で解決する場合はおよそ半年~1年,調停や訴訟等の法的手続きを行う場合には1年~数年程度要することもございます。前記のとおり案件に応じて異なりますので,ご相談の際に弁護士へお尋ねください。
相談は可能です。
ただし,現実の相続税申告や登記手続につきましては,弊事務所と連携している税理士や司法書士をご紹介させて頂きます。
弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
LINEでも相談予約いただけます!
当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
5、初回相談は無料
遺産相続のメニュー